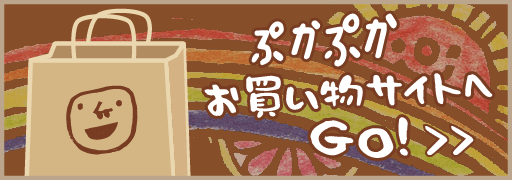ぷかぷか日記
養護学校時代
オオキしゃん (養護学校キンコンカン-⑤)

養護学校の教員をやっていた頃の話です。 トミちゃんは業務員のオオキさんが大好きです。一日一回は会わないと気がすみません。オオキさんに会いたくなると「オオキしゃん」とぼそっとつぶやき、もうそれだけでうれしくなって「ヒャ〜」ってコーフンした声が出て、顔はもううれしくてうれしくてくしゃくしゃ。 「ようし、オオキしゃんとこ行くか」 と、トミちゃんの手を引いて業務員室に向かいます。業務員室が見えてくると 「オオキしゃん、オオキしゃん、ヒャ〜ッ」 と、声がだんだんうわずって、うれしさに身もだえするように床にひっくり返ってしまいます。誰かのこと好きになるって、こういうことなんだとしみじみ思ったりしました。 業務員室の前まで来ても、すぐには飛び込んだりせず、ちょっとはにかむように業務員室の方をチラチラ見ながら、まわりをうろうろします。大好きな人に会える気持ちの高まりをちょっとずつ楽しんでいる感じなのです。トミちゃんは、ふだんは何かと大変な子どもなのですが、こういうところを見ると、ほんとうはすごくナイーブな心を持ってるんだ、となんだかうれしくなってしまいます。 そうして長い時間かけて気持ちの高まりを楽しんだあと、いよいよ業務員室に飛び込みます。オオキさんがいれば 「オオキしゃん!オオキしゃん!ヒャ〜ッ」 と抱きついたり、手を引っ張ったり、床にぺたんと座り込んだり、もう大変な騒ぎ。顔はもう幸せではち切れそう。 でも、机の上にお菓子があったりすると「オオキしゃん!」とうわずった声を出しながら、机に向かって突進。カメレオンの舌のような早業でお菓子を口に運んでしまいます。このあたりがトミちゃんのすごいところ。 トミちゃんが人の名前を言うのはオオキさんだけです。毎日いちばんつきあっている担任のぼくの名前は、くやしいことに一度も口にしたことがありません。まわりの教師たちの名前も口にしません。それはそのまま、トミちゃんがまわりの人をどんな風に感じているかを物語っています。 学校の中でいちばん子どもの面倒を見ていると自分で思い込んでいる教師の名前ではなく、いちばん地味な仕事をしている業務員のおじさんの名前を口にするというところが、なんとも痛快というか、トミちゃんの人間を見る目の確かさを思うのです。 学校には業務員さんのほか、スクールバスの運転手さんや添乗のおばさん、給食の調理員さんといった、子どもたちにいわゆる「指導」をしない人たちがたくさんいます。そういう人たちは子どもたちとごくふつうにつきあっていて、見ていてとても気持ちがいいです。そのことをいちばん感じているのは子どもたちだと思います。 「しばいごや」に登場したバスの運転手さん(中央蝶ネクタイのおじさん)とバスの添乗のおばさん(右側赤いドレスとサングラスの女性)、その後ろ、赤いシャツにサングラス、鼻に白い線を引いている怪しい男が若き頃のタカサキ。 「オオキしゃん」とつぶやいて、床にひっくり返ってしまうくらいうれしいトミちゃんを見ていると、ぼくも含めて教師というのは子どもたちに対して何をしているのかと思ってしまうのです。「タカサキぃ」とつぶやいて、床にひっくり返るくらい喜ぶ子どもがいないのはどうしてなんだろう、ということこそ、真剣に考えねばならない問題だと思うのです。 トミちゃんとオオキさんのおつきあいを見てると、人と人がおつきあいすることの豊かさのようなものを感じます。「指導」という関係は、こんな豊かさを作り出しているだろうかと思うのです。機会見つけてオオキさんのところへ教えを請いに行こうかと思っています。
『街角のパフォーマンス』が電子本に

30年前に書いた『街角のパフォーマンス』が電子本になります。電子本を作っている「22世紀アート」という会社から声がかかりました。 www.22art.net はじめは『ぷかぷかな物語』を国会図書館で見つけ、おもしろいので電子本にしませんか?というお誘いでした。でも、これは出版元の現代書館が電子本にする予定になっていたので(12月18日からアマゾンほか、紀伊国屋や楽天など、主要電子書籍店で購入できます)、『街角のパフォーマンス』を電子本にすることになりました。 制作の経費はこちら持ちです。20万円近い見積書が来ました。①本書籍の制作分析 ②テキスト化/PDF化 ③DTP制作など、これが妥当なものなのかどうかよくわからないので、『街角のパフォーマンス』の出版元太郎次郎エディタス社に聞きました。見積もりの内容、金額とも妥当なものだと言われ、あとはその金額が回収できるかどうかです。 で、22世紀アートに、経費が回収できるかどうかストレートに聞きました。100%保証はできませんが、今までの経験から十分回収できる本だと思います、の回答。その道のプロが本を読んで、そう言うのであれば、とGOをかけることにしました。 どうして30年前に書いた本を今、あらためて電子本の形で出すのかを考えてみたいと思います。 30年前に書いたとは言え、内容的に古いものではありません。30年前でありながら、そこで作り出したものは、時代のはるか先を行っていたような気がします。 「共生社会を作ろう」とか「ともに生きる社会を作ろう」といった言葉も、今ほど社会に広がっていない時代でした。障がいのある人たちに惚れ込み、一緒におもしろいことやろう!と、ただそれだけの思いでいろいろやっていたのですが、気がつくと、いっしょに生きる社会が小さいけれど自分のまわりにできていました。 支援とか指導ではなく、ただ一緒におもしろいことをやる。そんなフラットな関係で障がいのある人たちとつきあってきました。それが一緒に新しいものを創り出す元になったと思います。 演劇ワークショップも最初は「障がいのある人たちのために」みたいなところがありました。ところが始めてみると、演劇ワークショップの場の面白さを作り出しているのは彼らであり、彼らがいるからみんなが集まって来ることに気づきました。3回目くらいの反省会の時「支えられているのは私たちの方だね」と地域の人たちがいいました。何かやってあげる、という彼らとの関係が逆転したのはこの頃からです。彼らとの新しい関係がこうして始まったのです。 彼らに対して「あなたが必要」「あなたにいて欲しい」と素直に思えました。「共生社会を作ろう」とか「ともに生きる社会を作ろう」なんて言わなくても、そういった関係が自然にできたのです。それを考えると、『街角のパフォーマンス』で作った関係は、今のこの時代よりも先へ行っていた気がするのです。 社会の多くの人が、特に福祉施設の人たちが、障がいのある人に対して「あなたが必要」「あなたにいて欲しい」と思っていたら、あちこちで起きている虐待事件も、やまゆり園事件も起きなかったのではないかと思うのです。障害のある人たちに、日々接している福祉施設で、私たちが30年も前に作ったこんな関係が、どうしてできないのかと思います。支援はそういった関係なんか関係ないのでしょうか?社会から排除される彼らだからこそ、そういった関係が必要だと思うのですが… 目次見ただけでわくわくするような本です。 『街角のパフォーマンス』電子本は4月頃、電子本になります。発売日が決まりましたらお知らせします。
笑顔は魔物だったのかも

養護学校の教員をやっていた最後の年の話です。 遠くを見つめながら、ちょっと笑ったしのちゃんの横顔が好きでした。言葉をしゃべらないせいか、その横顔には深みがありました。ちょっとほほえんだ弥勒菩薩半跏思惟像のような、そんな深いやさしさをしのちゃんの横顔には感じていました。 しのちゃんのそのときのおだやかな気持ちが全部出ているようでした。しのちゃんがおだやかなとき、私はちょっと幸せな気持ちでした。 しのちゃんはクラスの中でいちばん障がいの重い生徒で、いちばん大変でした。なんの前触れもなく、いきなりぶん殴ってくるような生徒でした。一緒にトイレに行き、二人並んで用を足している最中にも、いきなりパンチが横から飛んできました。そんな状態でしたから、みんな1メートル以内には近づかない、といった雰囲気でした。 私もそうすればよかったのですが、どういうわけか私はしのちゃんが大好きでした。顔面を思いっきり殴られ、鼻の骨にひびが入って、鼻血を出しながらとっくみあいをしたり(高等部の生徒相手のとっくみあいはほんとうに大変でした)、胸に頭突きを食らって肋骨にひびが入ったり、雨のグランドで蹴り倒されてどろんこになったり、ほんとうにさんざんでした。ほとんど毎日のように殴られ蹴られ、もういい加減懲りてもいいのに、それでも私はしのちゃんが好きでした。 どうしてなのか、私自身、よくわかりませんでした。強いていえば、冒頭に書いたしのちゃんの遠くを見つめてちょっと笑う笑顔だったのかなと思うのです。あの笑顔を見ると、すべて許してしまうのです。しのちゃんの笑顔は私を幸せな気持ちにしたのです。殴られた痛み、悲しみ、怒りを全部忘れてしまうほどの幸せな気持ち。 あの笑顔は魔物だったのかも知れません。その魔物が今もぷかぷかを支えています。
『街かどのパフォーマンス』在庫あり−3

昨日学校に『芝居小屋』を作ったことを書きました。これは芝居をやる人、見る人、というふうに分けないで、みんなで一緒になって芝居を楽しむ熱い空間を作り出そうという試みでした。 『海賊ジェイクがゴンゴンすすむ』は『海賊太っちょジェイク』という絵本を元にした、本番までどうなるかわからない、わくわくハラハラする芝居でした。稽古をするたびにお話がどんどん変わり、小道具、大道具を作ると更に変わってしまい、子どもたちが動き回ると、あ、こういう動きがいい、とまた変わってしまう、実に自由な芝居作りでした。 海賊のお話なので、模造紙を30枚くらいつないで、フィンガーペインティングで海の絵を描きました。その細長い海の絵を『芝居小屋』の壁をぐるっと一回りするように貼り付けました。部屋の真ん中に座ってぐるっと見回すと、もうそれだけで海の真ん中にいる気分になります。耳を澄ますと「ザザザザ〜ン、ザザザザ〜ン」と波の音が聞こえてきそう。 そんな雰囲気の中でお客さんに波になってもらいました。 「ザザザザ〜ン、ザザザザ〜ン」 お客さんの体が気持ちよさそうに揺れます。何度も何度も繰り返します。波が大きくなったり、小さくなったり。それにあわせて声も体の動きも変わります。日がサンサンと照り、海はきらきらとまぶしい、とか何とかいいながら 「あっ! トビウオ! 」 と叫びます。お客さんの誰かを指さし 「はい、あなた、トビウオです。ピョ〜ンと飛びます。さあ、いいですか。せ〜の、ピョ〜ン」 というと、お客さんはほんとうにピョ〜ンと飛んでしまうのです。そういう雰囲気が「芝居小屋」にはあったのです。 「あっ、今度はイルカだ」 っていうと、イルカになって飛ぶ人がいました。 そんな中、海賊船が登場し、お芝居が始まります。波や魚をやったお客さんは芝居への集中力が違います。途中、風が吹いてくると、お客さんは風になり、嵐が来て雷が鳴ります。 「ビュ〜ン」「ビユ〜ン」「ピカピカッ!」「ぴか!」「ゴロゴロ!」「ゴロゴロゴロ」「ドッカ〜ン!」 なんとこの芝居40分もあって、役者もお客さんもくったくた、汗びっしょりになって楽しんだのでした。私自身は半年分をいっぺんに生きた気がした、と書いていました。 こんなにも熱気むんむんの空間が学校の中にできたこと、それが子どもも大人もみんなが一緒になって創り出したことがすばらしかったと思います。あれはやはり「ポラーノの広場」だったと、今あらためて思います。みんながあれほど自由になれる空間は、そう簡単に創れるものではありません。何ヶ月もかかって、芝居を創ったり、壊したりしながら、自由な雰囲気を創っていったのだと思います。 来年4月からまたワークショップを再開しようと思っています。こんな自由な空間が、今度は街の中にできれば、と思っています。ホームページにまたお知らせを載せます。時々チェックしてください。
『街かどのパフォーマンス』在庫あり−2

昨日『街角のパフォーマンス』の目次の紹介をしましたが、中身の紹介をします。 ひとことで言うと、障がいのある人たちとの新しいおつきあい、といったことになるでしょうか。養護学校の教員になり、最初の頃は子どもたちのやることなすことすべて想定外で、どう対応していいかわからず、おろおろする毎日でしたが、それでもよ〜くつきあってみると、心がホッとなごむような素敵な人たちでした。こんな素敵な人たちを養護学校へとじこめておくのはもったいないと、半年ほどたった頃、武蔵野の原っぱまで子どもたちを連れて行きました。そこでたくさんの人たちと出会い、それがすべての始まりでした。「あそぼう会」を立ち上げ、近所の公園であそんだり、「あおぞら市」に養護学校の生徒といっしょにうどん屋を出したり、演劇ワークショップをやったりしました。 演劇ワークショップは当初、彼らのためにやる、やってあげる、といった意識がどこかにあったのですが、やっていく中で、支えられているのは私たちの側なんだということがだんだん見えてきました。社会の中で排除される側にいる彼らと、あなたがいないと困る、あなたが絶対に必要、といった、社会とは逆方向のベクトルを持つ関係がワークショップの中でできたのでした。 それと平行して、学校の中でもワークショップの手法を使って、彼らといっしょに芝居を作り始めました。教師が台本を作り、その台本通りに子どもを動かす、といった方法ではなく、子どもたちと一緒に作り、子どもたちといっしょに舞台に立つ、という方法です。発表の場も、ステージではなく、教室を使って「芝居小屋」を作り、お客さんたちといっしょに舞台を作る、そんな発表の場でした。そこに集まる人みんなが、なんだかとても自由になって、宮澤賢治の「ポラーノの広場」のような場が出現したのでした。 『街角のパフォーマンス』はそういったことの記録です。読んでみる価値はあると思います。
『街角のパフォ−マンス』在庫あり

太郎次郎社エディタスという会社から、昔出した『街角のパフォ−マンス』という本を電子化していいかという問い合わせがありました。もう絶版になって、世の中から忘れられてるんじゃないかと思っていましたので、この問い合わせは嬉しいものでした。 太郎次郎社エディタスのホームページを見たら『街角のパフォ−マンス』在庫あり、とありましたので、興味のある方はどうぞお買い求めください。 http://www.tarojiro.co.jp/product/4015/ 養護学校で働いていた頃書いた本です。30代で、いちばんエネルギッシュに働いていた頃の物語です。目次の見出しを書くと 「ある日街かどににぎやかな舞台が…」「海のぬいぐるみとお獅子のうんこ」「本音をどかんと突き出す」「歌がしんしんとしみた」「アンタっていうセンセイはなんなのさ」「ヘビはネコをかみません」「どうにもお尻がムズムズしだして」「この女のヤロウをとじこめちゃおうぜ」「おまえたちはもう死んでいる」「海賊ジェイクがゴンゴンすすむ」「どうなっちゃうんだろうという不安がたまらない」「お客も役者もくったくた」「ちびくろさんぼがわっほいほい」「お父さんと二人でルンギーはいて」「近所のおばさん、舞台に立つ」「ひゃ〜どうしよう、どうしよう」「がっこうでもやきうやてんの」「黒い筆がベター、ペタッ、ペチャッと踊った」「『みちことオーサ』のめっちゃ楽しい上映運動」「べつに結婚しなくたって、子どもは産めるよ」「新聞投稿『身体障害児の乱暴』の波紋」「どうして電車の中でみんな黙っているんだい?」「教師たちの反応はさっぱり」「お母さんたちの話を聞いて、心が耕されているみたいだった」「あおぞら市にうどんや開店」「街の中にホッとする空間ができて」「机ひとつだけのうどんやではあったけれど」 あっ、おもしろそう、って思われた方は、ぜひ買ってみて下さい。アマゾンでも手に入るようです。
「テレビが、み、た、い!!!」「う〜、でも、が、ま、ん、する〜!!!」

養護学校に勤めていた頃の話です。 つう君はよく通る声で一人でおしゃべりします。当時、まだ若い工藤静香が大好きでした。なにかにつけ、工藤静香が登場します。学校であれば、別にどうということはないのですが、バスの中でこんなことを言ったこともありました。 「 くどうしずか、パンツ丸見え。いやらしいこといわない!」 いやらしいこといわない、と付け加えるあたりが、いかにもつう君らしく、笑いが倍になるのですが、それでも、内容的にはちょっと焦ってしまうものでした。 そんなつう君を引き連れて箱根の「ひと塾」でワークショップをやったことがあります。相変わらずわめいたりひっくり返ったりでなかなか大変なワークショップでしたが、それでも彼は参加者の中では圧倒的に人気がありました。 みんなで作った芝居のリハーサルがありました。ところがちょうどその時間につう君の好きなテレビ番組があり、「テレビみたい」「でも、がまんする」「テレビみたい!」「今日はがまんする!」と一人でぶつぶつ言ってました。つう君の気持ちの揺れがそのまま出ていて、楽しい一人漫才を見ているようでした。揺れの巾がどんどん大きくなって「テレビが、見たい!!」「でも、がまんする!!」「テレビが、み、た、い!!!」「う〜、でも、が、ま、ん、する〜!!!」と、このくらいになると、もう顔が苦悩にゆがんで、畳の上をのたうち回っていました。そのうち、とうとう限界を超えたみたいで、「ああ、もう、ダメ!!」と大声で叫んで、ダーッとすごい勢いで部屋を飛び出していきました。 結局、つう君抜きのリハーサルになりましたが、リハーサルの終わった頃、見たかったテレビを見終わったつう君が、すっきりした顔で帰ってきました。自分の気持ちにこんなにも正直な人はそういないよな、と思いました。 メイクをして本番。つう君は閻魔大王の役で、芝居の最後を締める主役です。その主役が肝心なところで、舞台の真ん中でわーわー叫びながらひっくり返ってしまい、ハラハラしましたが、それはそれで迫力ある閻魔大王になってしまうあたりが、つう君のすばらしい才能だと思いました。 何日か後に、ワークショップの参加者の一人から電話がありました。 「今度東京でワークショップやります。ぜひつう君はじめ、養護学校の生徒たちを連れてきて下さい。今までいろんなワークショップやりましたが、彼らといっしょにやったワークショップがいちばんおもしろいと思いました。ぜひ来て下さい」 ワークショップをやる時間が夜なので、 「彼らを誘っていくのは無理です」 といったのですが、彼らを送り迎えする車を出してもいい、とまでいいました。 彼らといっしょにワークショップをやって、そこまで惚れ込んだ人が現れたことに、感動してしまいました。ワークショップの場というのは、つう君はじめ、養護学校の生徒たちの魅力が、日常の世界よりも、もっとよく感じ取れるのだろうと思います。 来年はぜひそんな楽しいワークショップをやってみたいと思っています。ホームページにお知らせを載せますので、時々チェックして下さい。ホームページは「ぷかぷかパン」→「検索」
けんちゃん

養護学校で仕事をやっていた頃の話です。 子どもたちといっしょに手製の紙粘土で大きな犬を作ったことがありました。何日もかかって作り上げ、ようやく完成という頃、子どもにちょっと質問してみました。 「ところでけんちゃん、今、みんなでつくっているこれは、なんだっけ」 「あのね、あのね、あの……あのね」 「うん、さぁよく見て、これはなんだっけ」 と、大きな犬をけんちゃんの前に差し出しました。けんちゃんはそれをじ〜いっと見て、更に一生懸命考え、 “そうだ、わかった!” と、もう飛び上がらんばかりの顔つきで、 「おさかな!」 と、答えたのでした。 一瞬カクッときましたが、なんともいえないおかしさがワァ〜ンと体中を駆け巡り、 “カンカンカンカン、あたりぃ!” って、鐘を鳴らしたいほどでした。 その答を口にしたときの “やった!” と言わんばかりのけんちゃんの嬉しそうな顔。こういう人とはいっしょに生きていった方が絶対に楽しい、と理屈抜きに思いました。 もちろんその時、 「けんちゃん。これはおさかなではありません。いぬです。いいですか、いぬですよ。よく覚えておいてね」 と、正しい答をけんちゃんに教える方法もあったでしょう。「先生」と呼ばれる人は大概そうしますね。 でも、けんちゃんのあのときの答は、そういう正しい世界を、もう超えてしまっていたように思うのです。あの時、あの場をガサッとゆすった「おさかな!」という言葉は、正しい答よりもはるかに光っています。あのとき、あんな素敵な言葉に、そしてけんちゃんに出会ったことを私は幸福に思いました。
テツにはテツの人生が、私には私の人生が…

養護学校で働いていた頃、テッちゃんという子どもがいました。テッちゃんは食事をするにも、着替えをするにも、誰かの手助けが必要でした。歩くときも一人では無理でした。そんなテッちゃんのお母さんが、ある日連絡帳に書いてきたことを今でも鮮明に覚えています。 「私はテツがすべてという生き方はしていません。テツにはテツの人生が、私には私の人生が、という考えでいます。親子ともども同じ回転で人生を過ごしてしまう必要はないと思っています。」 テッちゃんは自分でいろいろやったりする子どもではありませんでしたが、ただそばにいるだけでこちらの気持ちがほっとなごむような、そんなやさしい雰囲気を持っていました。そういう存在感がいいな、と思っていましたが、「テッちゃんの人生」までは考えませんでした。 自分の子ども、しかも重度の障がいを持ち、何するにも手助けが必要な子どもの人生を自分の人生と並べながら語るお母さんに正直びっくりしました。子どもの人生を突き放して語れるだけの人生をお母さん自身が歩んできたのだと思います。 お母さんは絵を描くのが好きでした。化粧品を買うお金があれば絵の具を買ったと言います。それくらい夢中になれるものを持っていました。でも、テッちゃんが生まれ、その世話に追われる中で、絵筆を折ったそうです。「折った」といういい方がとても印象に残りました。 「折った」と語れるほどの人生をお母さんは歩んでいたのでしょう。だから「テツにはテツの人生が、私には私に人生が…」という言葉がさらっと出てきたのだと思います。 学校では「個別教育計画」が、福祉事業所では「個別支援計画」なるものがありますが、そこには「本人の人生」へ寄せる思いなどといったものはまずありません。関わる人間の人生が見えるような気がします。
しのちゃん

あるケースワーカーと話をしているとき、昔担任していたしのちゃんの話がでた。いちばん苦労しただけにいちばん懐かしい生徒だ。 しのちゃんは障害の程度でいえばいちばん重度で、いろいろ手のかかる生徒だった。中でもいきなりぶん殴ってくる暴力には本当に泣かされた。何の前触れもなく、いきなり「わーっ」と叫びながらぶん殴ってくる。ほとんど警戒していないので、げんこつがもろに顔に当たる。鼻の骨にひびが入ったり、胸に頭突きを食らって肋骨にひびが入ったり、鼻血を出しながら格闘したり、本当に大変だった。養護学校の教員は「なぐられてなんぼ」の商売、という人もいたが、しみじみ「ほんとにそうだ」と殴られながら思ったものだ。 ふつうならこういう人には1メートル以上は近づかないとか、いつも警戒態勢を取るとかするのだが、ぼくはそういうことは全くしなかった。1メートル以上近づかないどころか、いつもべったりそばにくっついていたし、警戒は全くしなかった。だからしょっちゅう殴られたりけられたりしていた。別に意識してそうしていたわけではなく、しのちゃんが好きだったのだ。殴られても、けられてもしのちゃんがなぜか好きだった。 しのちゃんは全く言葉をしゃべらなかった。その分、というか、笑顔が素敵だった。しのちゃんが笑うと、それだけでぼくは幸せな気持ちだった。殴られた痛みや怒りをいっぺんに帳消しにしてしまうくらいの魅力がしのちゃんの笑顔にはあった。この笑顔があったから、ぼくは殴られてもけられても、しのちゃんのそばにいつもいた。 養護学校だからこういう対応ができたが、社会に出ると、そうもいかない。卒業するときも、週一回くらい通える場所は何とか見つかったが、それ以外は施設で暮らすしかなかった。今どうしているのだろう、となんだか無性に会いたくなった。今度施設に電話してみよう。
ぷかぷかトピックス
障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。