今年も8月から演劇ワークショップをやります。今年はヨッシーの作品(添付した写真)を元にみんなでお話を作ります。











もう作品見てるだけでわくわくして、すぐにでもいろんなお話が生まれそうです。ヨッシーもいろんなお話を頭に浮かべながらこの作品を作ったのだと思います。ヨッシーのとてつもない創造力に圧倒されます。
あちこちにお話のネタが転がっています。
たとえばこのおじさんは顔を赤くして何を息んでいるんでしょうね。みんなで考えるといろんなお話が生まれます。ぷかぷかさん達といっしょにお話を作っていくので、とんでもなくおもしろいアイデアが飛び出します。それがお話の幅をグンと広げます。いっしょに生きることの豊かさを実感できます。

「この得体の知れない緑色の顔のおじさんはいったい何者?」「ここで何をしてるんだろう?」ってみんなで考えると、ヨッシーの作品のおもしろさが3倍にも4倍にもなります。


ヨッシーワールドに迷い込んだ3人のぬいぐるみ。わくわくするようなヨッシーワールドで何をしてたんでしょう。ちょっと考えてみよう。そうそう、三人に名前もつけよう。その方がぬいぐるみに親しみを持てて、お話が弾みます。イメージがぐんぐんふくらみます。
自分が迷い込むよりも、ぬいぐるみが迷い込んで、何をしたんだろうって考える方が考えやすいです。考えがいつもより自由になります。今年はこのぬいぐるみ達に助けられてお話が進みます。ぬいぐるみに感謝!

さて、どんなお話ができあがるのでしょうね。わくわく、ドキドキしながら第9期演劇ワークショップがスタートです。
演劇ワークショップの日程はこちら

9年続けてきた演劇ワークショップも、今年で最後です。みんなが自由になれ、自分の思いを表現し、新しい物語が生まれる貴重な場です。また違う形でやれればと思ってはいます。さてどうなりますか。
表現の市場も最後になります。とても残念な気がしますが、物事はいつか終わりが来るもの。そうではあっても、あの活気ある舞台がなくなってしまうのは、なんとも残念!「おーし、じゃ、来年からは私が」という人、大募集!
演劇ワークショップは、指の先まで自由になれるような時があります。そんな自由を味わってみたい方、ぜひご参加下さい。
問い合わせ、参加申し込みは









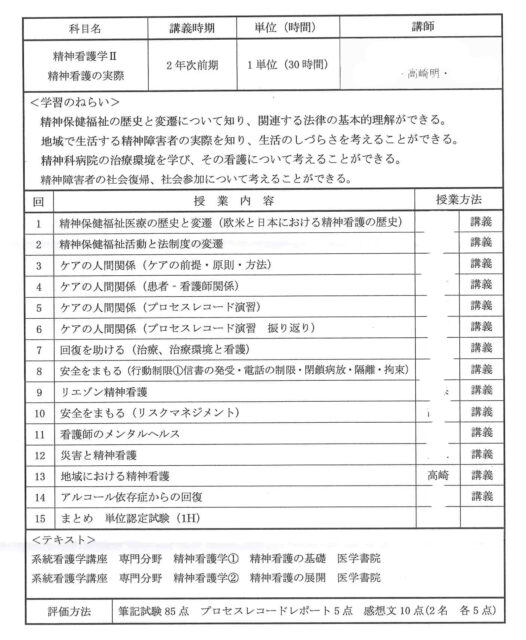



























まず感じたことは障がいをもつ人たちを支援する対象とした見方でなく、「共にはたらく・生きる」同志として地域を巻き込み(耕す)ながら一緒に活動し、そのほうが絶対楽しいということ。そして持続性があること。「多様性を認め合うインクルーシブ社会の実現を」とどこでも耳にしますが、今の社会の在り方は、教育、就労が障がいをもつ人たちとそうでない人たちとを分けた制度の上で成り立っています。
分離が進むほどその社会の規範に縛られて、障がいをもつ人たちがその多様性を認めてもらうどころか社会に合わせるために押し殺さなければならない、ますます支援、配慮の対象にされてしまう。
ぷかぷかさんのように障がいをありのまま楽しむ方法を作り上げれば、そこに生産性も生まれ、制度も使い倒し、地域も社会も豊かにしていくことを実現していけるのだなととても参考になりました。障がいをもった人たちと関わる仕事をされている方、学校教育関係の方にもぜひ読んでいただきたい一冊です。
何より、ぷかぷかさんたちがとても魅力的です。
だから、内容もおもしろくてあったかくてやさしい。
「好き」という思いで、まわりを巻き込んで、心を耕してやわらかくする。
その場も街も、ふかふかにしていく。
「あなたが好き」から出発した世界に人間の上下はない。
人を矯正していく支援はやはり無意識に「上下」があるのだと思う。
相手だけでなく、修正する側も自分自身が縛られていく。
自分を修正し、社会も修正しようとする。
それが今の息苦しさにつながっているのではないだろうか。
という訳で
先生や支援職にある人やサポートの組織を立ち上げる人には
ぜひ読んでほしいと思う。
他では得られない大きな気づきがあるはず。
最後の相模原障がい者施設殺傷事件への言及も必読です。
shop.pukapuka.or.jp
もう読んでしまった方は、ぜひアマゾンのカスタマーレビューを。